
『無添加』と聞いて
「体に良い」「安心できる」というイメージを持つ人も多いですよね。
ただし、実際には『無添加』と表記された食品にも
天然由来の添加物や加工に必要で含まれることがあります。
食品添加物による効果、役割を知っていて損はありません。
知って賢く『めちゃゆる無添加』
一緒に勉強していきましょう♪
食品添加物と健康:本当に危険なのか?
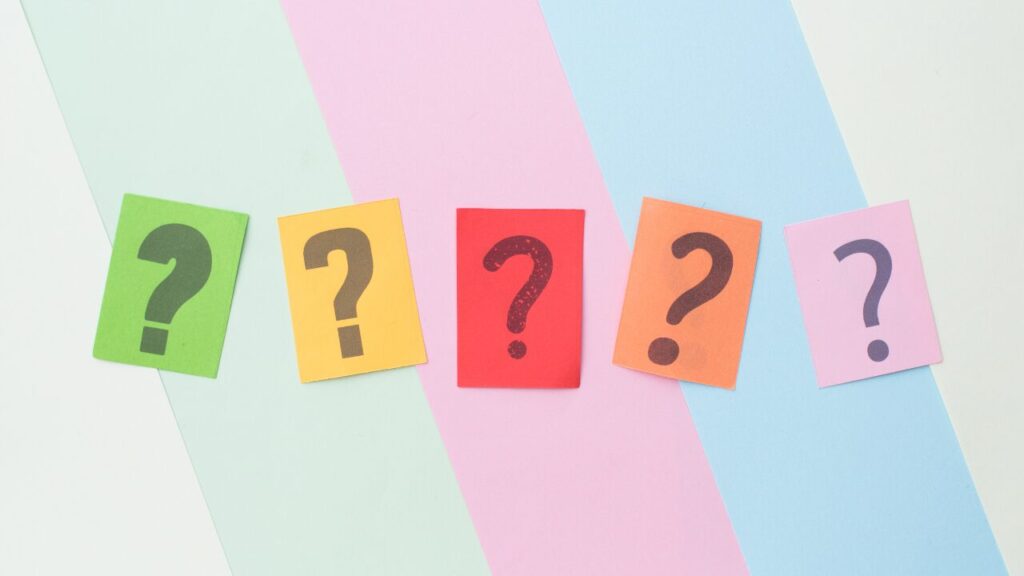
食品添加物について世の意見として
「体に悪い」
「危険」
そんな言葉を目や耳からの情報で得たことはありませんか?
食品添加物を使用される理由として
大まかに3つに分類することができます。
・保存性や安全性のため
・色味や匂いで魅力的にアプローチするため
・コストカットするため
コロナ以降、食品に対しての健康意識が高まり
『添加物の危険性』『無添加』『オーガニック』など様々情報を
目にするようになったのは確か。
マイナスな情報ばかりが目立つ中で
誤解していたこともありました。
正しく理解すれば
『怖いもの』『悪いもの』ではありません。

・長期保存で食品ロスを減らすことができる
・見た目や香りを良くなる
・大幅なコストカット
・安価でに入る
意図は違いますがそれぞれ必要な役割を果たしています。
摂取すると健康に悪影響を及ぼす可能性もあるため
正しい理解と使い方が大切と考えます。
健康についての食品添加物の影響

食品添加物が健康に与える影響について
・使われる量や種類
・摂取の頻度
上記の事を理解しなくてはなりません。
例えば
保存料や着色料の中には、大量に摂取すると健康リスクが高まるものもあります。
消化器官への負担、アレルギー反応、子どもの発達に考慮される可能性が高いとされています。
しかし、日本における食品添加物の多くは
政府の厳しい基準をクリアしています。
気付かないうちに日常的に口にしていることも少なくありません。
少ない摂取量であれば
健康に大きな影響を考えることは少ないとされているようです。
でも体に入るものだからこそ、慎重に選んで購入したい!!
添加物は悪者?その真実は

「添加物=悪」というイメージを持つ人も多いですが
実際にはそうとも限らないこともあります。
例えば
私たちがよく食べるパンにも添加物が使われています。
その多くは保存性の意味でビタミンやミネラルといった栄養素も添加物の一種として分類されることがあります。
さらに食品添加物の中には自然由来の成分も添加物として使われることがあります。
例えば
ビタミンC(アスコルビン酸)やクエン酸などは
酸化を防ぐために使用される自然由来の添加物です。
『無添加』と書かれた商品にも、自然由来の添加物として含まれていることもあります。
完全に無添加の生活を目指すことが難しいと感じる世の中。
どんな添加物が使われているのか?
その量が適切なのか?
食品添加物を使用する意図は?
知識を深めて正しく理解
購入前に食品表示を確認することで回避できるものもあります。
かめさんは表示を見ないで購入することがあるよ。
そんな時でも『めちゃゆる無添加』だから
「ま〜、、、いっか。」
体に入る総量を減らすスタンスなんだね。
食品添加物の種類と用途
食品添加物は大きく分けて二つに分かれます。
・指定添加物
・一般食品添加物
指定添加物は、特定の用途に応じて使用されるものとして国が定めたもので。
数百種類が存在しています。
着色、保存性、味を調えるために使われます。
指定された食品添加物の役割
指定された添加物にはそれぞれの役割があり
その用途に応じて使われます。
代表的なものとして
- 保存料:食品の腐敗やカビの発生を防ぐ。長期保存が可能
- 酸化防止剤:食品が空気や光によって劣化するのを防ぐ
- 着色料:食品の見た目を美しくし魅力的にする
- 甘味料: カロリーを抑えながら甘味をつける
- 増粘剤:食品にとろみをつけたり、形を整える
| 分類 | 役割 | 例 |
|---|---|---|
| 保存料 | 食品の腐敗を防ぎ、保存期間を延ばす | ソルビン酸、安息香酸 |
| 着色料 | 食品の色をカラフルにする | カラメル色素、タール系着色料 |
| 甘味料 | 食品に甘みを加える | アスパルテーム、スクラロース |
| 酸化防止剤 | 酸化を防ぐ、食品の品質を守る | ビタミンC、トコフェロール |
| 増粘剤 | 食感や粘り気を増す | ゲル化剤、ペクチン |
| 調味料 | 味を整える、風味を良くする | グルタミン酸ナトリウム(MSG)、イノシン酸 |
| 乳化剤 | 油分と水分をわかりやすくする | レシチン、モノグリセリド |
無添加・天然と添加の違い
「無添加」とは、基本的に添加物を一切使用していない食品を指します。
しかし、残念なことにすべての食品が添加物を使用しない『無添加』ではないようです。
自然由来の添加物は比較的安全性が高いとされています。
例えば、ハーブやスパイスは自然な腐敗防止効果を持っており、化学的な添加物を使わずに食品の保存性を高めることができます。
気になる人は無添加食品を選ぶ際、パッケージの表示をよく確認して
「本当に必要な添加物?」
理解して見極めることが重要です。
自然由来の添加物を名前、役割、詳細

自然由来の添加物について
どんなものがあるかをまとめました。
| 名前 | 役割(何のために使われるか) | 詳細(何からできるか) |
|---|---|---|
| ナタマイシン | 防腐剤 | 自然にあるもので、カビや酵母から食べ物を守る |
| ナイシン | 防腐剤 | 乳酸菌という菌が作るもので、悪い菌から食べ物を守る |
| 紅麹色素 | 着色料(食べ物を赤くする) | お米を発酵させてできる自然の赤い色 |
| カロチノイド色素 | 着色料(食べ物を黄色やオレンジ色にする) | 野菜や果物のある自然の色で、にんじんやかぼちゃに多い |
| クチナシ色素 | 着色料(食べ物を黄色くする) | クチナシの実という植物から取れる自然の黄色 |
| クロロフィル | 着色料(食べ物を緑色にする) | 植物にある自然の緑色 |
| ビートレッド | 着色料(食べ物を赤くする) | ビーツという野菜の根から取れる自然の赤い色 |
| β-カロテン | 着色料(食べ物をオレンジ色にする) | にんじんやかぼちゃのある自然のオレンジ色 |
| スピルリナ色素 | 着色料(食べ物を青くする) | スピルリナという藻(も)が作る自然の青い色 |
| キシリトール | 甘味料 | トウモロコシや木の繊維から取れる自然の甘味料 |
| ラカンカ抽出物 | 甘味料 | 羅漢果(ラカンカ)という果物から取れる自然の甘味料 |
| ステビア | 甘味料 | ステビアという植物の葉から取れる自然の甘味料 |
| エリスリトール | 甘味料 | 果物や発酵食品にある自然の甘味料 |
| ビタミンC | 酸化防止剤 | 果物や野菜にある自然のビタミン |
| ビタミンE | 酸化防止剤 | 植物の油やナッツにある自然のビタミン |
| クエン酸 | 酸化防止剤 | レモンなどの柑橘類にある自然の酸 |
| ローズマリー抽出物 | 酸化防止剤 | ローズマリーというハーブから取れる自然の成分 |
| ペクチン | 増粘剤(食べ物をとろっとさせる) | みかんやりんごなどの果物にある自然の成分 |
| アルギン酸ナトリウム | 増粘剤 | 海藻から取れる自然の成分 |
| カラギーナン | 増粘剤 | 海藻から取れる自然の成分 |
| ゼラチン | 増粘剤(食べ物を固める) | 動物の骨や皮から作る自然の成分 |
| 寒天(アガー) | 増粘剤 | 海藻から作る自然の成分 |
| 酵母エキス | 調味料(旨み) | 酵母という菌から取れる自然のうまみ成分 |
| 乳酸 | 調味料(酸っぱさを加える) | 乳酸菌が作る自然の酸味 |
| レシチン | 乳化剤(食べ物を分かりやすくする) | 大豆や卵黄から取れる自然の成分 |
上記の表は自然由来の添加物のごく一部です。
案外、食品表示内で見かけるものも少なくありません。
自然由来のものと分かれば
なんとなく手に取りやすく感じるのは私だけ?
まとめ

食品添加物は
私の日常生活に必要な役割を果たしています。
しかし、正しく使用されることが大前提です。
安全に守るために必要なものも多いですが、健康面に気をつけた方が良いものも存在します。
現日本では食品添加物について正しい知識を持つことを必要とされています。
自身の健康
家族それぞれに合った選択
難しく考えない
『めちゃゆる無添加』
体に入る食品添加物を減らすことで心と体の健康を応援します。

